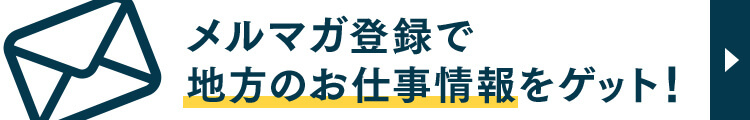「Local Link」は、地方にある魅力的な企業や経営者の想いをストーリー形式で知ることのできる求人メディアです。求人募集中の企業については、インタビューの最後に求人情報と応募フォームが掲載されています。
今回は、株式会社AlgaleX 代表取締役 高田大地 様です。
【Profile】
株式会社AlgaleX
代表取締役 高田 大地
1989年神奈川県茅ヶ崎市出身。早稲田大学法学部卒。大手総合商社にてM&A、事業再生、ベンチャー投資を担当。その後、水産養殖の課題解決を目指し、商社在職時に投資したスタートアップにCFOとして転職。2021年3月、沖縄県うるま市で株式会社AlgaleXを設立。2023年現在は「泡盛粕」を活用した、DHAと旨味を高含有する藻「うま藻」を中心とした事業を展開している。
身体に良いだけでなく美味しい藻「うま藻」
弊社の事業は泡盛を製造する際の副産物である「泡盛粕」を活用した、DHAと旨味を高含有する藻「うま藻」の企画製造販売が中心です。
うま藻にはサプリメントと食品があります。計画段階ではサプリメントとして売り出そうと考えていたのですが、研究開発の途中で「美味しくなる」ことに気が付き、それならば美味しいを軸に売り出すのが良いのでは、と現在は食品を中心に販売しております。
それ以外にも藻類の特殊開発技術を用いた未利用資源の価値化事業に取り組んでいく予定ですが、まずは唯一無二の美味しい藻「うま藻」を使った事業化からですね。

なぜ藻を育てるのか
みなさんが安価に買っている養殖魚は、DHAがないと育ちません。そのDHAを摂取するために天然魚を粉にした魚粉を食べることで、DHAを摂取します。商社に勤務していた頃、港に隣接する飼料メーカーに行くと巨大なサイロ(貯蔵タンク)1つ分が魚粉で埋まっているのを見て、大量の天然魚が使われて養殖魚が育つ事に衝撃を覚えたことを覚えています……。
この状態だとサステナブルではないので、魚を減らさず持続可能なDHAを作ること、これが私たちのビジネスのスタートであり、根本になります。
当社で培養しているのはオーランチオキトリウムという種類で、自然界で最初にDHAを作り出した藻です。DHA含有量は青魚の10倍以上、アミノ酸系の栄養素もたくさん含んでいる、まさに「魚の塊」です。
しかし、藻を安定的に育てるのは難しく、特にオーランチオキトリウムに関しては培養に失敗した企業も多々あります。そんな中、弊社はただ培養に成功しただけでなく、旨味をまで豊富にする培養方法を見つけました。
海外にはオーランチオキトリウムの培養をしている大手の会社があるのですが、美味しくないので抽出してDHAオイルとして販売しています。当社はそのような競争マーケットには入らず、美味しい藻という独自の価値を生かして食品として戦っていきます。

創業に至るまでのストーリー
私のビジネスキャリアは新卒で丸紅に入社して、豚鳥牛魚の餌を世界中から集めてくる飼料穀物チームに配属されたところから始まっています。
飼料穀物チームに紐付けで財務経理に異動することになり、中途採用の優秀な先輩たちに色々なことを教えてもらいながら、会社を数字から見ることを学び、その後は丸紅が港を持っていた南米の穀物倉庫の立て直しに携わりました。
6年目ぐらいに、穀物で新規事業をやることになりました。2014年に魚粉の一大産地であるチリ、ペルーで大不漁となり、輸出が規制され、丸紅の先にいる養殖業者は飼料価格の高騰により大打撃を受け、零細養殖業者の一部は倒産するという事態に追い込まれました。養殖魚の餌を魚だけに頼っていると、いずれ同じようなことが起きると確信し、魚を減らさないで養殖魚の餌を作る方法を探すべく、代替タンパクや代替DHAに目を向け始めました。
その一環として私たちのチームはインドネシアのスタートアップに投資しました。そこでやっていたのは、パームオイルの廃液から藻を育ててDHAを作る、まさに今のビジネスの原型です。私自身は、途中でこちらのスタートアップにCFOとして転職し、しばらくインドネシアに滞在していました。しかし、ファウンダーがコロナで亡くなったことをきっかけに、当時研究者として在籍していた多田と私で当該技術を何としても形にすべく、AlgaleXを起業しました。
多田は「未利用資源を活用した藻類発酵技術を社会実装したい」、私は「魚を未来に伝える仕事がしたい」という思いを持っています。AlgaleXの社名の由来については、Algae(アルガ)が藻の意味で、それを色んな価値に変えていきますよという意味でXを付けました。

沖縄県うるま市で起業したきっかけ
沖縄県のうるま市で起業した理由は、パイロットスケールの培養設備を日本で唯一時間貸しで借りられるからです。
ジャーファーメンターという発酵槽(微生物の大量培養に用いる装置)があるのですが、単独で買うとかなり高額です。90リットル程度の設備なら大学の研究施設にもありますが、商業規模で使えるパイロットスケールの大きさを借りられるのはここだけで、そのために沖縄で起業しました。
沖縄は東京と違って小さな地域なので、人との繋がりが重要です。沖縄の人は色んなことに関心を持ってくれ、おせっかいを焼いてくれる土地柄です。それが良いか悪いかはその人の捉え方によりますが、沖縄に円もゆかりも無かった当社にとってはとても有難かったです。地域で仕事をするメリットはこのようなところにあるのではないかなと思います。

泡盛粕にたどりついた奇跡
藻を培養する過程で、アミノ酸の供給源として酒粕などの未利用食品を食べさせます。はじめは焼酎粕やビール粕を使っていたのですが、ある時、当社の向かいにある新里酒造さんから泡盛粕をいただいて藻を育ててみたところ、藻の常識からは考えられませんが、とても美味しくできました。
私や、藻類発酵で日本屈指の技術者の多田には「藻はまずい」という固定観念がありました。藻は栄養素はあるけれど味が美味しくないので、色々とマスキングを施して食べるのが一般的です。しかし、うま藻は普通にお酒のつまみとして食べても美味しいのが最大の特長です。もちろん、当初の目的通り、DHAは魚の13倍も含まれ、旨味とDHAの塊と言える藻と言えます。
泡盛粕はこれまでは捨てられていた食品廃棄物です。そんな泡盛粕を活用できて、かつ藻が美味しくなるということで、泡盛粕を本格的に使うことになりました。
今後5年でうま藻を世界中に普及させ、将来的には「魚に魚を食べさせない養殖」を実現する
当社は、起業当初からずいぶん大変でしたが、雨降って地固まるという言葉があるように、結果的に次の道が見えてくるという経験をしています。「ピンチをチャンスとして捉える」というのが会社のアイデンティティです。
また「データや研究に対して真摯であること」が研究ルールであり、行動指針です。当社は技術の会社なので、そこがしっかりしていないとダメだと思っています。
これから先の5年間はうま藻を日本だけでなく、世界中に普及させていくことが中心になります。うま藻はあくまで一原料です。鰹節や昆布は料理に必要ですが、主役になるものではありません。でも、色々なところに入っています。うま藻も同じように、旨味食材としての市民権を得た状態を作りたいと思います。
5年間のうちに「美味しい藻」という新しいジャンルを確立し、うま藻がそのカテゴリーの定番商品になるようにしていきます。新しい旨味、DHAの供給源になるだけでなく、完全植物性なのでビーガンの人にとっても画期的なアイテムです。例えば、チャーハンに振りかけると簡単に海鮮チャーハンになります。食の楽しみを広げる新しいコンテンツになる可能性がうま藻にはあると思っています。
5年後には会社の土台をしっかりさせて、そこから先は「魚に魚を食べさせない養殖」に注力していきます。美味しい食体験を通じて「美味しい食の裏側は、今どうなっているのだろう」と興味を持ってもらえるようになれば嬉しいです。人々の意識が変わることが、魚に魚を食べさせない養殖の布石になると思います。
採用では、ベースのマインドセットを一番大事にしています。スキルは後からついてくるものですし、ビジョンもやっていくうちにだんだんしっくりくるものだと思いますが、マインドセットはなかなか変わりません。相手に目線を合わせられる人。目の前に困っている人がいたら、真摯に「見て、聞いて、行動できる」マインドを持っている人と一緒に仕事をしていきたいと思っています。

![Local Link[ローカルリンク]](https://local-link.professional-studio.co.jp/wp-content/uploads/2024/02/a-02.png)